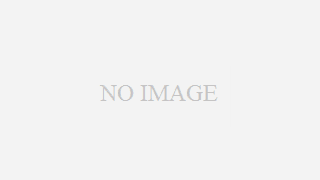 ユナイテッド関連
ユナイテッド関連 第10節 フォレスト戦
結果は2-2確かに嫌な予感はした。アウェー監督交代で息を吹き返してきた。昨シーズンダブルそれでも最近の勢いでイケるかとも思ったけどそんなに甘く無かったですね。立ち上がりはスロースタートだったけど、コーナーからカゼミロのヘッドで先制点。このあ...
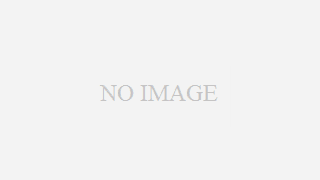 ユナイテッド関連
ユナイテッド関連 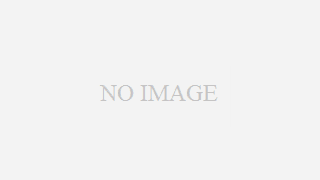 ユナイテッド関連
ユナイテッド関連 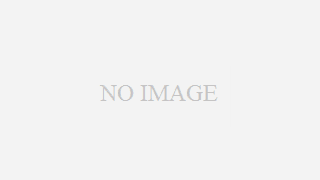 ユナイテッド関連
ユナイテッド関連 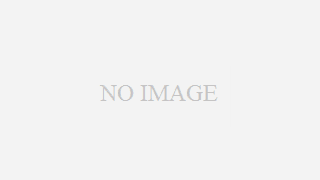 ユナイテッド関連
ユナイテッド関連 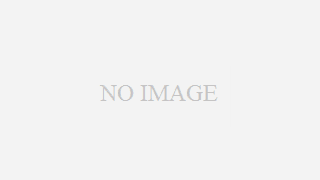 ユナイテッド関連
ユナイテッド関連 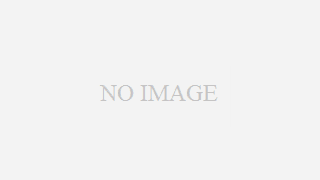 ユナイテッド関連
ユナイテッド関連 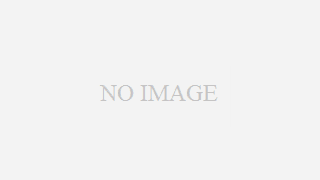 Uncategorized
Uncategorized 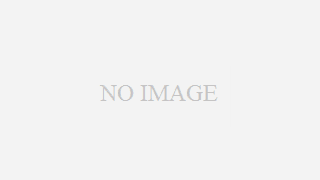 Uncategorized
Uncategorized 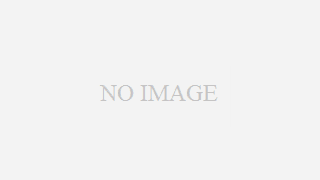 Uncategorized
Uncategorized 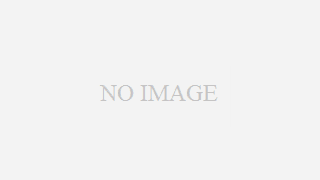 ユナイテッド関連
ユナイテッド関連